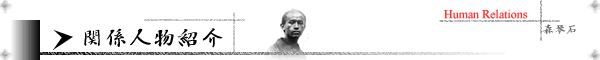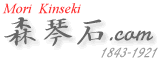 |
|
森琴石の師匠や先輩・友人知人など、また琴石の周辺の人物を紹介します
■雅友・知友 な に ぬ ね の
項目内で使用度の多い資料について(各項目で、書名・資料名のみにする場合があります)
◆「浪華摘英」(浪華摘英編纂事務所・三島聰恵発行・大正4年8月)、「続浪華摘英」(発行兼編纂三島聴恵・大正5年12月)=大塚融氏(元NHK記者・数寄者研究家・経営史研究家)よりご提供頂きました
◆「大阪人物辞典」=三善貞司著・清文堂刊・平成12年
◆森琴石日記
(明治42年8/3 〜10/7、明治45年2/15〜7/31、大正元年8/1〜10/5 間での断片的に残るもの。翻刻者=成澤勝嗣氏(神戸市立博物館)
長阪雲在(ながさか うんざい) |
|
●関連事項=調査情報「平成17年9月【2】・関連資料「一致帖」 |
|
和歌山藩士ナリ 字は士孔 通稱三郎 雲在と號ス ※長阪家は元和5年7月(1619)、徳川頼宣が駿河より和歌山へ移封されたのに伴って田辺与力となり和歌山に移り住んだ「横須賀一統」に当たる。藩の複雑な内部諸事情を経た後、文久3年(1863)紀伊田辺より松阪御城番として赴任、殿町に住んだ。雲在は、紀州藩に尽力した浜中陽照院の海弁大僧正に感じる事多く、海南の「長保寺」で僧侶として修行を積んだという。([松阪市史第14巻]=松阪市教育委員会文化課 などより) ◆「三重先賢伝」(浅野松洞著・昭和6年)ご提供=松阪市教育委員会 文化課 (二) 長阪雲在、名は徳、字は子潤、雲在と號す、伊勢松阪の人、子時濱中長保寺に僧たりし事あり、其れより何れの寺院にか僧籍を置き、専ら南畫を研究す、後ち還俗して諸國を歴遊し、和歌浦に來往、畫筆に親しむ。それより更に居を大阪に移し各地を漫遊、居ること正に十數年、遂に同地に於て歿す、曾て明治三六年、五回博覧會の浪華に開かるゝや、青緑松林山水の圖を出品し、二等賞を贏ち得て、宮内省御買上の名誉を得しことあり、歿年享年」とも今詳しかならず。 ◆「紀州郷土藝術家小傳」(貴志康親著・昭和九年)ご提供=近藤壮氏(和歌山市立博物館) (三) |
永田暉明(ながた てるあき)=永田碧桐(ながた へきとう) |
|
●関連事項=「平成17年9月 【1】」 |
|
●佐賀藩藩士、天保九年九月廾九日蓮池村に生る。 ●碧桐又は有終と号し詩文に長ず。 ●慶応元年東都に遊び聖堂に学ぶこと二年、維新の際東西に奔走し国事に侭す所あり、明治四年廃藩置県後蓮池大参事、続いて大属となり、十二年西松浦郡長次で神崎郡長に任ぜられる。 ●廾ニ年官を罷めて県会議員となり、廾九年八月佐賀市長に挙げられ、当時の難問たりし好生病院の県営開始を解決し、又学区統一を図る等市政の為に尽くす所妙なからず。 ●三十一年市長の職を辞するや浩翰なる蓮池史の編輯を了し、三十七年芙蓉時社を起して後進を誘致し、其詩社は猶今日に継続せらる。 ●著書に憲法管見、蓮池舊話、同藩史、燈火漫言などあり。 ●晩年神戸令息益一氏の許に寄寓し、近藤元粋・藤澤南岳等と交遊し益々文名を馳せたり。 ●大正十二年三月十九日歿す。享年八十六。 ◆資料=「佐賀県歴史人名事典」(佐賀県立図書館) |
永田方正(ながた ほうせい) |
●関連事項=最新情報「平成17年1月」 |
〈一) 天保15年三月一日〜明治四四年八月二二日(1844〜1911)
|
◆「愛媛県百科大事典」(愛媛新聞社刊) より |
(二) 1838(天保9)〜1911(明治44)
|
◆「北海道大百科事典」(昭和56年8月20日・北海道新聞社発行)より |
| 関係人物一覧 |
| 師匠・先輩たち(南画・儒学・洋画法・系図)雅友・知友(あ・か・さ・た・な・は・ま) |
| HOME |
| Copyright (c) 2003 morikinseki.com, all rights reserved. |