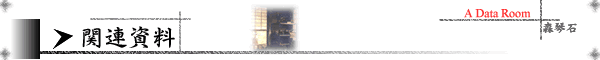中野 理 (なかの おさむ)文
昭和十七年に神戸市に転勤するまで、私は十年間も高田の病院にいた。毎夏赤倉に避暑される入澤達吉先生を伽羅山荘にお尋ねするのが楽しみの一つでもあった。それが亡くなられる年までつづいた。
そんなある夏「君の祖父は偉かったんだよ」 と、いって、私に先生の随筆楓萩集を下さった。その中の関寛斎の長崎伝習館滞在学日記に・・・・・・
文久元年六月十九日。越後の人、相共に蘭船に往き虎を観る。一個のアフリカ人が虎を処置するこ と其言の如し、或は手を出し、或は叫び、或は犬と戯る事あり。帰路浪華平安の諸大家の画帖を見る。
後国蒲原郡今町 入澤恭平
同 竹山裕卜
五泉 中野森之輔 |
*著書(入沢達吉)註 竹山は余之の母の父 中野は母の姉の夫
*筆者(中野)註、入沢、中野は共に三十歳。 |
竹山は両者の義父とあれば五十歳くらいと推定され、いささか疑義を覚え、入沢文明(達吉の子)と荻野久作博士を通じて竹山行雄(竹山屯の孫)さらに八代裕卜の妻竹山静子と長岡の竹山道治博士とに質した。
それによれば、裕卜は一代から八代までの世襲名で、これは別名裕雨と呼ぶ四代裕卜(幕府の奥医桂川甫賢に師事。明治四年十一月十七日死)であるが、あるいはそのころ三十二歳の五代裕卜(別名享、蘭医川本幸民の門下。ポンペに師事せず。明治十一年三月五日死。四十八歳)とも思われるが、確信なし。以上。
釈然たらざるも筆者(入沢達吉)の註に従って事をすすめる。
七月二十五日 朝食後、午後より角力を観る。夜に入りて帰る。鈴木、入沢、中野、内藤、岩佐純等なり。
(筆者註 長崎伝習館在学日記の所有者佐藤道夫博士に質して、下の二項を追記する)
六月二十一日 ゾンタク 午前の課業を勤め、午後より冬衣を晒らし越後の人を尋ぬ。
七月二十七日 ゾンタク 島氏を中野氏へ送る。
この中野森之輔(これは助)は私の母の父で、雪江の青年時の名である。
ポンペ朋百はシーボルト(1823―29及び1857-62の再度来朝)に遅れること三十四年、安政四年―文久2年(1857-62) 江戸幕府に招かれ、長崎第二次海軍伝習所医官として来朝したものであった。
伝習所門人録には松本良順、佐藤尚中、司馬凌海、入沢恭平、長与専斎、戸塚文海、橋本節斎、名倉知文、 吉雄圭斎、川北玄等の名がみられる。
そのころ越後から長崎への留学は、汽船による欧州留学時代の労苦よりも遥かに困難なものであったらしい。入沢恭平の日記によれば往路に六十一日を要した、ということでも想像がつこう。水盃して門出したことはもちろんであったろう。
いずれにしても当時、舅と姉婿、妹婿の三人が医学勉強のため、相前後して長崎に出かけたことは、向学の志まことに旺なりというべきで、たしかに先覚者ではあった。
入沢恭平は上記の如く侍医頭入沢達吉の厳父であるが、竹山裕卜は新潟病院長兼医学校長を勤め、後、竹山病院を創設した竹山屯の父である。今は人も知る荻野久作博士が、そこの院長である。
ところが一人中野森之助のみは医道を進まず、画人となった。 何故だろう?
その間の消息を詳らかにすることはできない。当初、森之輔の名は私にも判らなかった。「続五泉町史」(昭和二十五年九月)の著者佐藤俊英からも照会があったが確答ができなかった。
私がレルヒの研究にたずさわって三十年。とうとう最後の仕上げともいうべきレルヒ遺稿の翻訳に 三ヵ年を費やして完稿したとき、私の妹が「執念のレルヒが終ったら、次は中野の家史をしらべなさい。子供たちの代になったら、何にも判らなくなりますよ」
いわれてみれば、もっともな話、それで先般新潟に行き、生家の蔵に預かってもらっていた古文書 や反古紙を持帰って整理しはじめた。その中に北条泰時の貞永式目や元禄四年版の観世流謡本百番を 発見したのも喜びであった。そんなわけで、その中から中野森之助の日記こそ発見できなかったが、 漢詩や和歌とで織りなした他の旅日記や彦雄の名で詠んだ歌集数冊、旧幕時代から明治新政期にかけ ての辞令等を発見したので、おぼろげながら雪江のリリーフを彫ることができた。
中野雪江、幼名久平、青年時森之助、後に静一郎、字は寛、
五泉町の、今は五泉市、中野家九代久左衛門の長子として、天保二年六月生る。
幼時より画を父楓泉に学び、嘉永二年椿椿山の門に入り、師の没するまで六ヵ年間画業修業。
時に二十三歳。嘉永七年会津、奥羽遊歴。文久元年二月より三府を経て長崎に遊学。ポンペに師事す。
多面銕翁、木下逸雲、清人雨亭、王克三、憑鏡如、鈕春松等に読画を請う。翌文久二年十月帰国す。
その後東京に遊ぶこと数度、明治15年二月北陸道遊歴数ヶ月、京阪に到って墨客と画談。
後、中国、四国、五幾、東海道を経て東京へ。更に奥州を遍歴して十二月帰国している。
はじめ眠雲、瞑雲等と号したが後雪江、清静堂、枕石山房と称し、花鳥をよくした。三男三女を挙ぐ。
彼は舅竹山裕卜と義弟入沢恭平とともに長崎へ遊学、ポンペに師事したが(註、竹山と中野は聴講程度と思われる)医道には進まず、絵筆をとって美術の世界に生きた、けだし青年森之助も、或はそ の進退去就に迷い、大いに悩んだであろう。
しかし、もともと中野の家は医家でなく、室町時代の五泉城主第四代中野玄正より出て、代々町役人を つとめ、 八代中野久左衛門以降苗字帯刀御免、大庄屋格兼町年寄役を仰せつかっていた。従って長子であったがため医道に進むよりも、世襲の本業を継がねばならぬ運命にあった。
時恰も維新の黎明であったが、大爆発の余震など、一般庶民には感知できなかったことかもしれない。しかし、その庶民も黒船の渡来、米蘭露英仏5カ国との条約調印、安政の獄、桜田門の変と、 ひた押しに押してくる洪水のような西洋文明なるものには多大な関心を持ちはじめていたには違いない。森之助の場合も、西洋医学勉強のために、ポンペに師事したものか、或は当初から西洋文化の 吸収が目的で、長崎伝習所の門をたたいたものか・・・・・それは判らない。
しかし、ポンペによって西洋文化の多くを摂取しえたことは間違いあるまい。蘭船に行って、はじめて 虎の生態をも見た。多数洋画を観賞する機会もあった。その影響か慶応年間に、彼は絹地に水彩画の肖像を画いている。
幕府の崩壊と年を同じくして父を失った彼は明治新政に職を奉じた。最初の役は御払掛り(御蔵宿五千表)。明治四年のことであった。その後、計算掛、戸長を経て副大区長、官等十七等で明治十一年に官を辞 した。時に四十八歳であった。
雪江は退官後、画道に専念し、詩歌を作り、風月を友とした。従って文人墨客の知友多く、師椿椿山を はじめ 、滝和亭、森琴石、堀井玩仙、木下逸雲、水原梅屋、大沼蓮斎、吉田晩嫁等とは特に親交があった らしい。また清国人との交りも深く、自宅に長期滞在させた画人、書家等の文人も多い。その中に胡鉄梅、 衛鋳生、王治本、王冶梅、朱印然、王琴仙等の名も画も書もみられる。中でも朱印然の如き、外国人雇人 届を出して詩文書画教師として、月給三十円にて一ヵ年、雇いれている。明治十八年のことである。
第一図は胡鉄梅の筆になる雪江像である。彼については神戸とのつながりもあるので、一稿を新にしたい。
(註 このHP上では図は入れられないので、以下第二図・第三図とあるが、省略する)
第二図は西園寺公二十歳時の書である。雪江が好んで画を画き、自らも梅痴と号したほどで、公もそれを書かれたものと思う。中納言公望は明治維新の折、仁和寺宮嘉彰親王の会津征討越後口総督の一人として越後に来り、長岡落城後は新発田に駐屯した。城主が米沢に逃れて空になった村松城に、会津桑名兵が立篭り、五泉に塁を築いたが、八月四日先鋒三浦梧楼らによって塁は一蹴された。雪江は「八月の御討入来格別の骨折り奇特の至り・・・・・・・」の感状に添えて、酒一樽を元年十一月にもらっている。そんなわけで、公の五泉町巡視の折にでも立寄られて、書き与えられたものか、あるいは公の幕下にあった軍務病院診療師の竹山屯が雪江の義弟であった関係から、新発田へ参伺した折にでも賜ったものか、詳らかではない。
雪江の画は今から見れば、まこと稚拙とも見えるが、当時は今日の日展にも比すべき明治十五年第一回大阪絵画共進会、同十七年第二回東京絵画共進会に出品入選し、死亡前年の二十三年の大阪同会では、三等銅賞を受けている(第三図)。彼は好きな画筆を携えて、各地を歴遊したので、今日では思わぬところで、彼の絵にめぐり会う事がある。
手許にある文化十五年の五泉町五人組家並順絵図と天保五年の中野家絵図面を見ると、伊勢の川と、そ の分流に挟まれた長二等辺三角形の邸内には、土蔵三棟、酒倉、穀倉、材木小屋等があり、稲荷も祀り、墓まで見られる広大な屋敷である。底辺が町の本通りに面していて、十軒の長屋門と一軒の独立借家がある。本屋の南面する上段の間、次の間、三の間は客室で、縁をめぐらし、築山を配したおく庭に面している。そこには伊勢の川分流から引いた清冽な水をたたえた池が見られる。緋鯉真鯉が美しい魚紋を描きながら泳いでいたことであろう。 恐らくこれらの客室が彩管をふるい、詩歌を談じ、花に詠み、月を賞でた文人たちの 集いのところであったのだろう。
この庭に詠めると思われる数首を彦雄(雪江の雅号)の歌集より拾ってみよう。
さくとさく庭の流に山吹の
色き庭を移してよするささ浪
春雨に翅しほれて鶯の
声なつかしの長閑けさ
椿花落水に流るるをみて
ちりかかる庭の垣根も白妙に
霜かとばかり身ゆる志ら菊
白露の光もすすしのきはなる
月にかけたる笹かにの糸
秋されば垣根も白妙に
霜かとばかり身ゆる志ら菊
今、その道に立てど、昔を偲ぶよすがもない。夏草やの夢の跡には、町がそこに立つ。ただ五泉の町 に恥じぬ昔変らぬ清澄な伊勢の川水が勢いよく流れている。
朱印然の記す雪江筆画帖の跋に
余遊越知契惟雪江先生而巳
朝暮与処盃酒諭心而花香月
艶時必期共酔雖費百金不惜
他人若謂吾与子狂其狂正得
吾与子之楽古人云画家要胸
中無識塵然後可入佳境殊
不知佳境即此狂中得也・・・・・・・
かく画人として生き、ついに家を傾けた雪江は・・・・・
事たりぬほとこそよけれ世の中は
みつれはかくる月に知るらん
くもりなきみきかし玉の光さえ
砕けはきゆる夢の世の中
と述懐するほどの淡々たる心で、明治二十四年二月十二日、彼の生涯に幕をおろした。時に六十一歳 であった。明治天皇の書の指南、吉田晩嫁の筆になる墓碑が五泉市三本木隆善寺の墓所に見られる。
終りに本篇を草するに当り、懇切なる御教示を忝うした東京入沢文明、新潟荻野久作博士、同竹山静子、 長岡竹山道治博士、長崎大三谷靖教授、市川佐藤道夫博士(順不同)の諸氏に対し、深甚なる感謝の意を 表するものであります。(兵庫県)
|